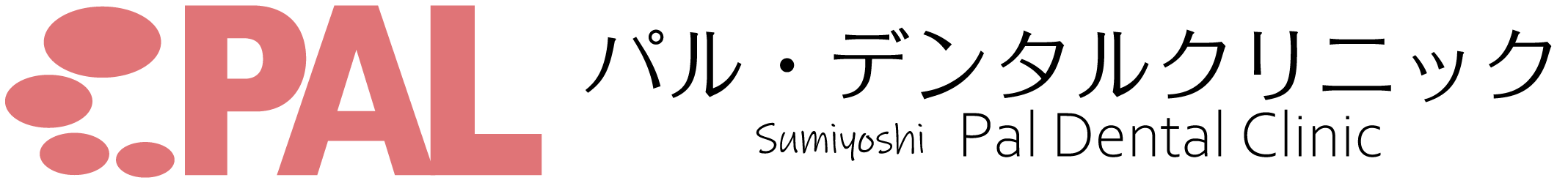根管治療について
はじめに ~ 根管治療とは?
 根管治療(こんかんちりょう)は、歯の内部にある神経(歯髄)が感染した場合に行う治療で、「歯の根の治療」や「歯内療法」とも呼ばれます。虫歯が進行して歯の神経まで達した場合や、歯の根の先に膿が溜まる根尖病変が生じた場合に必要となります。この治療の目的は、感染した神経や細菌を除去し、歯の内部を徹底的に清掃・消毒することで、再感染を防ぎ、歯を保存することです。適切に根管治療を行うことで、本来抜歯が必要とされる歯でも、長期間機能させることが可能になります。
根管治療(こんかんちりょう)は、歯の内部にある神経(歯髄)が感染した場合に行う治療で、「歯の根の治療」や「歯内療法」とも呼ばれます。虫歯が進行して歯の神経まで達した場合や、歯の根の先に膿が溜まる根尖病変が生じた場合に必要となります。この治療の目的は、感染した神経や細菌を除去し、歯の内部を徹底的に清掃・消毒することで、再感染を防ぎ、歯を保存することです。適切に根管治療を行うことで、本来抜歯が必要とされる歯でも、長期間機能させることが可能になります。特に当院ではより精度が高く再治療率を下げることが可能な「精密根管治療」を行っています。
根管治療が必要なケース
深い虫歯(う蝕の進行)
虫歯が歯の神経(歯髄)まで達すると、炎症(歯髄炎)が生じ、激しい痛みを伴います。初期の虫歯であれば、詰め物や被せ物で対応可能ですが、歯髄に炎症が広がると根管治療が必要になります。
根尖性歯周炎(歯の根の先の感染)
過去に根管治療を受けた歯で、内部に細菌が残っている場合、歯の根の先に膿が溜まり、慢性的な炎症が続くことがあります。この状態を放置すると、歯槽骨の吸収や歯の動揺が進み、抜歯が必要になることがあります。
外傷による歯髄壊死
転倒や強い衝撃によって歯にダメージを受けると、歯の神経が壊死し、内部が感染することがあります。見た目では問題がなくても、時間の経過とともに歯の変色や根尖部の腫れが生じることがあり、根管治療が必要になります。
歯の亀裂・破折
歯に細かいひび割れ(クラック)が入ると、細菌が根管内に侵入し、感染が広がることがあります。この場合、早期に適切な根管治療を行わなければ、抜歯のリスクが高まります。
根管治療の種類
根管治療には、治療の目的や進行状況に応じて「抜髄(ばつずい)」「感染根管治療(再根管治療)」「歯根端切除術」の3つの主要な治療方法があります。それぞれの治療方法の目的と手順を詳しく解説します。
抜髄(ばつずい)~ 初めて根管治療を行うケース
抜髄とは、虫歯が神経(歯髄)に達し、炎症(歯髄炎)や感染が進行した場合に行う根管治療です。神経を取り除くことで痛みを解消し、感染の広がりを防ぐ目的があります。
抜髄の流れ
- 局所麻酔を行い、痛みを抑えながら治療を開始
- 虫歯に侵された部分を削り、歯髄腔(歯の内部)を開放
- リーマーやファイルを用いて、歯髄(神経)を除去
- 根管内を洗浄・消毒し、細菌感染を防ぐ
- 根管をガッタパーチャという充填材で封鎖
- 必要に応じてクラウンを装着し、歯を補強
抜髄のポイント
- 歯髄の炎症が早期であれば、適切な処置で歯の寿命を延ばせる
- 根管の形態が複雑な場合、マイクロスコープを使用すると治療精度が向上
- 適切な充填が行われないと、根管内の細菌が増殖し、再治療が必要になることもある
再根管治療(感染根管治療)~ 過去の根管治療後に問題が再発したケース
再根管治療とは、以前に根管治療を受けた歯で、再び感染が発生した場合に行う治療です。適切な治療が行われなかった場合や、歯の内部に細菌が残っていた場合、数年後に根尖部(歯根の先端)に病変が生じることがあります。
再根管治療の流れ
- 被せ物(クラウン)や土台(コア)を除去し、根管を再露出
- 以前に充填された根管材料(ガッタパーチャ)を取り除く
- 根管内の細菌を徹底的に除去し、薬剤を用いて洗浄・消毒
- 根管を再び充填し、密閉して再感染を防ぐ
- 被せ物を再装着し、歯を補強
再根管治療のポイント
- マイクロスコープを使用すると、感染部位をより正確に除去できる
- 根尖部に大きな病変がある場合、根尖切除術が必要になることもある
- 成功率は初回治療より低下しやすいため、慎重な処置が求められる
歯根端切除術~ 根の先の病変が大きいケース
歯根端切除術(しこんたんせつじょじゅつ)は、根尖部(歯の根の先)に膿が溜まり、通常の根管治療では治癒しない場合に行う外科的治療です。
歯根端切除術の流れ
- 局所麻酔を行い、歯茎を切開して根尖部を露出
- 感染した根尖部分と膿の溜まった病巣を取り除く
- MTAセメントなどで根管の先端を封鎖し、再感染を防ぐ
- 歯茎を縫合し、術後の経過を観察
歯根端切除術のポイント
- 根管治療だけでは治癒が難しい場合に適応される
- MTAセメントを使用することで、封鎖性が向上し、成功率が高まる
- 術後の回復期間が必要となるが、適切な管理で歯を長く残せる
根管治療の成功率と再発リスク
根管治療の成功率
一般的な根管治療の成功率は60~80%程度とされていますが、精密根管治療(マイクロスコープ+ラバーダム防湿)を併用すると、成功率は90%以上に向上します。
再発の原因
根管治療が適切に行われなかった場合、以下の要因によって再発のリスクが高まります。
- 根管内に細菌が残存している(清掃・消毒が不十分)
- 根管充填の封鎖が不完全(細菌の再侵入が起こる)
- クラウンの適合精度が低い(細菌が侵入しやすくなる)
- 噛み合わせのバランスが崩れている(歯根に過剰な負担がかかる)
精密根管治療のメリット
当院では「精密根管治療」に対応、極めて精度の高いマイクロスコープ精密治療を行っています。
マイクロスコープの使用
肉眼の約20倍の拡大視野で治療を行うことができ、根管内の細部まで正確に処置が可能になります。
ラバーダム防湿の徹底
治療中の感染リスクを低減するために、ラバーダムと呼ばれるゴムシートを使用し、根管内を無菌的な環境に保つことが重要です。
CT診断による正確な診断
従来のレントゲンでは確認できない細かい根管形態や感染の広がりを立体的に評価できるため、より正確な治療計画を立てることができます。
根管治療を受ける際の注意点
1. 治療回数と期間
一般的に、根管治療は1~3回の通院が必要ですが、症例によっては4回以上かかる場合もあります。また、難治性の症例では歯根端切除術などの追加治療が必要になることもあります。
2. 治療後の痛み
根管治療後に軽度の痛みや違和感が続くことがありますが、通常は数日~1週間で落ち着きます。ただし、強い痛みが続く場合は、追加の処置が必要になることがあります。
3. 治療後の歯の強度低下
神経を除去した歯は脆くなりやすく、破折リスクが高まるため、適切な補綴処置(クラウン装着)が推奨されます。
まとめ ~ 根管治療で歯を長く残すために
- 根管治療は感染した歯髄を除去し、歯を保存するための重要な治療
- 深い虫歯、根尖病変、外傷などが原因で根管治療が必要になる
- 精密根管治療(マイクロスコープ+ラバーダム+CT診断)で成功率を向上
- 再発を防ぐためには、治療後の適切な補綴処置と定期的なメインテナンスが重要
「歯を長く健康に保つために、正しい診断と適切な根管治療を受けましょう。」